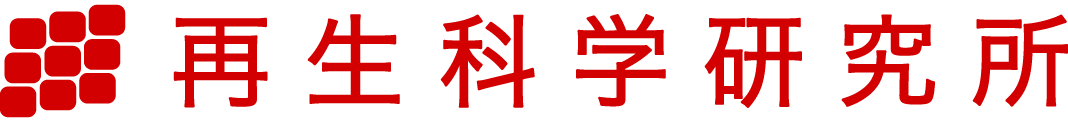
暖かくなってきて、過ごしやすい季節になりました。
皆さんは、二十四節気(にじゅうしせっき)をご存知でしょうか。
二十四節気とは、1年を24等分して期間に分けて季節を表すもので、約15日ごとの節気に分けたものです。
よく聞く言葉で、春分(しゅんぶん)、夏至(げし)、秋分(しゅうぶん)、冬至(とうじ)などがあります。
これらをまとめて二十四節気といい、全部で24つもあります。
どうして二十四節気というものが作られたのでしょうか。
日本では、明治5年まで、旧暦が使われていました。
旧暦は、月の満ち欠けを基準にしていて、実際の季節とずれが生じるので、3年に1度、閏月(うるうづき)を入れて調整しています。
季節がずれてしまうと、農業など、生活に影響を与えてしまうので、二十四節気というものが作られました。
二十四節気は太陽の動きを元にしています。
今の日本でも、太陽を基準にしている「太陽暦」が使われています。これを新暦といいます。
4月~5月の二十四節気の一覧、読み方、2025年の日付を紹介します。
清明 せいめい 4月4日
穀雨 こくう 4月20日
立夏 りっか 5月5日
小満 しょうまん 5月21日
聞いたことが無い言葉もあるのではないでしょうか。
他の季節にどんな二十四節気があるのか、興味を持った方はぜひ調べてみてくださいね。
季節の変わり目は体調を崩しやすく、新年度となり、疲れもたまりやすいです。
弊社のDDS 水溶性ベータグルカン サプリメントは健康な身体の維持をサポートしてくれます。
美味しくて食べやすいゼリー状の健康食品です。
毎日を生き生きと過ごすために、是非活用ください。
